── 投票という「声」を、どうすればもっと届くものにできるのか?
📝 本章は筆者の個人的な見解に基づいた雑感をまとめたものです。内容は一般的な政治論とは異なり、現代の日本における選挙の風景に対する問題意識と問いかけを含んでいます。過度な断定を避けつつも、率直な感情と現状への懸念を共有するための“余談”としてご覧ください。
✅ なぜ、選挙に「がっかり」してしまうのか?
東京都知事選挙、兵庫県知事選挙──注目されるべき選挙でも、違和感が残る場面が増えています。
- 候補者よりも話題性優先のメディア報道
- モラルを疑われる人物の立候補と党の対応
- SNSの一部で過熱する印象操作
- 有権者の“考える材料”が足りないままの投票
特に選挙速報特番は、単に「誰が通ったか」を早く知らせるだけの内容になりがちで、政策や論点に深く踏み込まれることが少なくなっています。
❗ 選挙特番に登場するコメンテーターが芸能人中心となり、質問も陳腐化している現状は、メディアの“伝える責任”の低下を象徴しているかもしれません。
✅ 「選ばれる人」が狭すぎる日本
- 世襲やタレント候補の割合が多く
- 選挙参謀がついた“演出された候補”が有利になり
- 政策の中身よりも“外見”や“発信力”が重視される
選挙公報も上手く作られれば一見まともに見えますが、
❗ 中身を見ようとすればするほど「それっぽく仕上げてくる候補者」が優位になる傾向があるのが実情です。
表面的な比較では、本質を見抜くことが難しいというのが率直な実感です。
✅ 無投票という静かな危機?
地方議会では、無投票当選が多数発生しています。
- 多選・高齢の現職がそのまま残る構造
- 対立候補を擁立する体力・資金がない地域政党
- 「現状は良くないけど、誰に任せても変わらない」という諦め
決して“立候補者が一人”というだけの問題ではなく、政治そのものが「市民の関心の外側」に追いやられている構図があります。
❗ 無投票が続けば、「交代可能性」が失われ、行政への緊張感も失われてしまいます。
✅ メディアの“空白”とSNSの“過信”
選挙期間中の特番は時間制限が厳しく、本当に聞きたい論点に踏み込めず、各候補の主張も抽象的に終わりがちです。
一方SNSでは、
- 一部の投稿が過剰に拡散
- 意図的な印象操作や偽情報も混在
- 有権者が情報の出どころを確認する習慣がまだ弱い
結果として、
情報の“量”は多くても“質”が伴わず、判断材料が整わないまま投票日を迎えてしまう──そんな現象が多発しています。
✅ では、どうすれば「変わる」のか?
理想論ではなく、現実的な視点から考えた改善の糸口:
| アクション | 目的 |
|---|---|
| 候補者への質問会や市民対話の拡充 | 見た目や演出ではなく“思考の中身”を見る |
| 公共放送での政策深掘り番組の強化 | 短時間でなく継続的に論点を見せる |
| 若年層向け選挙教育の充実 | 選ぶ力=社会参加の基礎を養う |
| 政治家の実績の可視化 | 人気ではなく“行動”で評価する文化 |
✅ 「見抜く力」を育てることが、最終的には「まともな候補者が通る」社会の前提になるのです。
✅ 最後に──「選ぶ」とは、「未来に責任を持つ」こと
政治を変えるには、まず選挙の現実を冷静に受け止める必要があります。
- SNSや報道に流されすぎない
- 「誰でも立てる」が「誰でもいい」ではない
- 投票した後も、その人の言動を“見る文化”を育てる
🎯 選挙はゴールではなく、スタート地点。
そして──
✨ 選択は、いつだって、あなた次第。
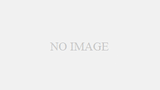
コメント