📝 AI(ChatGPT)による執筆をもとに構成したものです。本記事は、筆者のMMT(現代貨幣理論)支持の立場に基づいています。内容の正確性については、ご自身でもご確認ください。
✅ みんなが知らない「通貨のうまれ方」
👧「ねぇざんだかくん、1万円札って、いったいどこで作ってるの?」
🧾「それはね、日本銀行……略して“日銀”が作っているんだよ」
そう、日本銀行は日本で唯一お金を発行できる場所です。
でも「紙を刷ってるだけ」じゃありません。現代のお金の多くは、実は**数字上のお金(電子的な記録)**です。
たとえば:
- 銀行口座にある「預金」もお金
- スマホで使う「電子マネー」もお金
お金とは、紙幣という「モノ」ではなく、信用と仕組みによって生まれる道具なんです。
✅ 日本銀行のしごと
日本銀行には大きく4つの役割があります:
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 発券銀行 | 紙幣(日本銀行券)を発行する |
| 政府の銀行 | 国庫金の管理や国債発行業務を担う |
| 銀行の銀行 | 民間銀行の当座預金の管理・貸出 |
| 金融政策の司令塔 | 金利や資金供給の調整で景気を安定させる |
🧾「日銀は、“経済の心臓”のようなもの。お金という血液を全身に循環させて、経済という体を元気に保っているんだよ」
✅ お金の創造:信用創造って?
👧「じゃあ、銀行が貸してるお金って、どこから来るの?」
🧾「実はね、預金を貸してるわけじゃないんだよ」
ここで出てくるのが信用創造という仕組みです。
簡単に言うと:
銀行は「貸し出し」をすることで、新しくお金を“作る”ことができる。
たとえば:
- あなたが銀行から100万円を借りる
- 銀行はあなたの口座に「100万円」と書き込む
- この時点で、世の中に“新しい100万円”が生まれた!
これは民間銀行が日銀に預けた準備金をもとに、何倍もの貸出を行うことで起こる現象です。
この増え方を「信用乗数(しんようじょうすう)」と呼びます。
✅ 日銀が動けば何が変わる?
たとえば、日銀が「景気をよくしたい」と考えたら?
- 金利を下げる(=お金を借りやすくする)
- 国債を買い、市場にお金を流す(量的緩和)
そうすることで:
- 銀行の貸出が活発に → 企業が投資しやすくなる
- 雇用や給料が増える → 家計が元気に → 消費が伸びる
景気が“熱くなりすぎた”ときは逆にブレーキをかけます(=金利を上げる、資金を絞る)。
✅ 政府と日銀、どう違う?【MMT視点】
👧「政府と日銀って、どっちもお金に関係してるけど、どう違うの?」
🧾「うん、よく聞いてくれた。実はここが一番大事なんだ」
| 主体 | 主な役割(MMT的視点) |
|---|---|
| 政府 | 国債を発行して支出することでお金を生む(通貨の発行主体) |
| 日銀 | 金利を操作して支出が行きすぎないように調整する(金融政策) |
| 税金 | 使われたお金を回収する手段。財源ではなく、インフレ抑制や所得再分配のために存在 |
👧「えっ!?税金って、政府のお財布じゃないの?」
🧾「実は違うんだよ。政府はまず国債を発行して支出することで、お金を新しく生み出してる。
税金は、そのあとで一部を回収する道具なんだ」
✅ 正しい順番はこう!
- 政府が支出(例:医療・教育・年金など)
- その支出でお金が世の中に流れる
- 景気が過熱したら → 税金で一部を回収して調整する
🧾「つまり、支出が先・税金は後なんだよ。これは政府が“通貨発行権”を持っているからこそできることなんだ」
✅ 「国の借金」って、ほんとに問題?
👧「じゃあ“国の借金”って、心配しなくていいの?」
🧾「その“借金”って言い方が誤解の元なんだ。
政府の国債は、実は“通貨を発行した記録”に過ぎない。自国通貨で返せるから、破綻リスクはゼロに近いんだよ」
👧「ええっ、じゃあ、増税しなくてもいいの?」
🧾「“物価が安定しているうちは”ね。
増税が必要なのは、“お金を使いすぎてインフレになったとき”だけなんだよ」
✅ まとめ:お金は「生まれる」もの
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| お金は紙幣だけじゃない | 銀行の貸出や政府支出でも“生まれる” |
| 政府は「支出が先」 | 税金で“財源を確保する”という考えは誤り |
| 日銀は調整役 | 景気に応じて金利や資金供給量を調節する |
| 税金の目的は? | 財源確保ではなく、インフレ抑制・格差是正のため |
🎉 次回は、第7章『せいさくのコンパス』へ!
金融政策と財政政策のちがい、そして目的と手段のすれ違いについて、わかりやすく解説していきます!
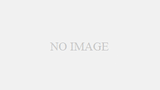
コメント